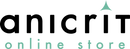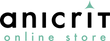おせち料理の意味と由来|食材に込められた願いと食べ方のマナー

はじめに
お正月といえば欠かせないのが「おせち料理」。彩り豊かな重箱に詰められた料理には、ひとつひとつに意味や願いが込められています。今回は、おせち料理の由来や歴史、代表的な食材の意味、そして食べ方のマナーまでを詳しく解説します。
おせち料理の由来とは?
『おせち』はもともと節句の料理
おせちの語源は「御節供(おせっく)」という言葉で、もともとは五節句など季節の節目に供えられる料理を指していました。やがて、正月に食べる特別な料理が「おせち料理」として定着し、現代まで伝わっています。
また、保存食としての意味もあり、かつて正月三が日は台所の神様を休ませる意味で火を使うのを避けていたため、日持ちする保存食としての意味合いもありました。冷蔵・冷凍が普及する前の知恵でもあります。
おせちの重箱と詰め方の意味
重箱は「めでたさを重ねる」縁起物
おせち料理は重箱に詰めて供されるのが一般的です。これは「福を重ねる」「喜びを重ねる」といった願いが込められた日本独自の美しい文化です。

段ごとの意味
-
一の重(祝い肴・口取り):縁起を担ぐ料理が中心
-
二の重(焼き物):主に魚や肉などの焼き物
-
三の重(煮しめ):根菜類を使った煮物が中心
※地域や家庭によって異なりますが、このような構成が基本となります。
代表的なおせち料理とその意味

黒豆:まめに働き、健康に過ごせるように
「まめ」は“健康”や“勤勉”を意味し、一年を元気に過ごせるよう願いが込められています。
数の子:子孫繁栄
ニシンの卵である数の子は、たくさんの卵があることから「子だくさん」「家族繁栄」の象徴です。

昆布巻き:「喜ぶ」にかけた縁起もの
「よろこぶ=昆布」から、お祝いの席にふさわしい食材とされています。
田作り(ごまめ):五穀豊穣
昔、カタクチイワシを田の肥料にしたことから「豊作祈願」の意味があります。
栗きんとん:金運・財運アップ
黄金色の栗きんとんは、「金運上昇」や「商売繁盛」を願うおせちの定番です。
おせち料理の食べ方とマナー

①食べる順番に決まりはないが「一の重から」が基本
おせちは正式な場では「一の重」から順にいただくのが礼儀とされていますが、家庭では好きなものから楽しんでOKです。
「重箱の四隅には最初に箸をつけない」といういわれもあります。それは「四隅が空くと、幸運が家の隅々まで届かなくなる」という意味によるものです。
②感謝の気持ちでいただく
そもそもおせち料理は、日本の伝統的な新年の食事で「家族や友人と一緒に食べることで、幸せな一年を過ごせるように祈る」ためのものです。
また、新年の幸せをもたらすために、元旦に各家庭にやってくる「年神様」へのお供物という意味もあります。
おせち料理は「お正月くらいは家事をせずにゆっくりするためのもの」とも言われますが、それだけでなく、「年神様を水に流さないようにする」という意味で、水仕事の必要ない保存食を用意するという意味もあるのです。
新しい年を迎えられることや周りの人々への感謝を持って、おせち料理をいただきましょう!
③祝い箸の使い方
両端が細くなった「祝い箸」を使うのが一般的で、「神様と人がともに使う箸」という意味が込められています。
祝い箸の長さは、約24cm(8寸)が一般的です。これは、日本では昔から末広がりの「八」が縁起が良い数字とされているからです。
真ん中が太く両端が細くなっており、片方は神様が使う方と言われているため、取り分けなどで箸先に持ち替えて使うのはNGです。
お正月の祝い箸は、松の内(元旦~1月7日)もしくは三が日(元旦~1月3日)の間は、同じ箸を使うのが習わしですが、きちんと洗って、衛生面には注意しましょう。
まとめ|おせちは“食べるお守り”
おせち料理は、ただの年始のごちそうではなく、“家族の健康”や“幸せな1年”を願う意味が込められた大切な文化です。現代ではアレンジや簡略化も増えていますが、その背景にある想いを知って食べることで、お正月の食卓がより温かく豊かな時間になるでしょう。
次回はおせちの選び方やポイント・失敗しないタイミングなどを
2026年のアニクリオンラインストアのおせちと併せて紹介していきます。