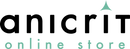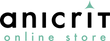「出産祝い」とは?
赤ちゃんの誕生を祝福し、母子の健やかな健康とこれからの子育てを応援する気持ちを込めて贈る「出産祝い」。家族や親戚、友人、同僚など、身近な人に赤ちゃんが生まれた際に贈るのが一般的です。
出産はとてもデリケートなライフイベントのひとつ。「母子ともに無事であること」を確認してからおくるなど、タイミングや相手の体調への配慮やマナーには必ず注意しましょう。

「出産祝い」の5つの基本マナー
基本マナー1.出産祝いを贈る相手
出産祝いは、身近な親族や友人、職場の同僚・上司などに贈るのが一般的です。特に、出産の報告を直接受けた場合や日頃から交流のある相手には、何らかの形でお祝いの気持ちを伝えたいものです。また、形式よりも「無事に出産してよかったね」という気持ちを大切にし、無理のないタイミングと方法で贈ることが、思いやりのあるマナーです。
基本マナー2.出産祝いを贈る時期
出産祝いを贈るタイミングは、赤ちゃんの誕生を確認した後、母子ともに少し落ち着いてくる生後7日目以降〜1か月以内が理想とされています。
ただしこの頃は慌ただしく、母親の体調も不安定なため、出産祝いを渡しに訪問する際は必ず事前に連絡を入れましょう。実家で過ごしている母子も多いこの時期、宅配で贈る場合はどこ宛てに送るのがよいか確認し、相手に再配達や転送といった受け取りの負担が無いように配慮しましょう。
生後1か月をすぎた場合も、「遅れてごめんね」とお詫びを添えて、精一杯お祝いの気持ちを伝えれば問題ありません。

基本マナー3.出産祝いの相場
出産祝いを送る際に気になる金額相場。贈る相手との関係性によって異なり、一般的に親族には1万円〜3万円、友人や同僚には3千円〜1万円程度が目安とされています。あまりに高額すぎると、相手に気を遣わせてしまったり負担に思われたりすることもあるため、相場に見合った金額で選ぶのがマナーです。
なお職場関係では連名で贈るケースも多く、その場合は1人あたり1,000〜3,000円程度を出し合うことが多いです。贈る品物が実用的で、相手にとって使いやすいものであれば、価格よりも気持ちが重視される傾向にあります。
基本マナー4.出産祝いの熨斗・表書き
出産祝いにはのし紙を付けるのが基本マナーです。
水引は“何度あってもよいお祝いごと”を意味する「紅白の蝶結び」を用いましょう。のし紙の表書きには「御祝」「御出産御祝」「祝御出産」などと書き、下段には贈り主の名前を記載します。複数人で贈る場合は連名でも構いません。のし紙をかけることで、一層丁寧な贈り物として、お祝いの受け取ってもらえるでしょう。
熨斗のマナーについてはこちらでも詳しく紹介しているのでぜひ参考にしてみてくださいね。

基本マナー5.出産祝いに適した贈り物
現代では、贈り物の種類も多様化しており、ベビー用品やおもちゃ、現金、ギフトカードなど、相手のライフスタイルに合わせた実用的な贈り物が選ばれるようになっています。
実用的なアイテムとしては、おむつケーキ(おむつをケーキの形にデコレーションしたもの)やスタイ、オーガニックコットンの肌着などが定番です。また、必要な育児用品の購入に使えるギフトカードや、カタログギフトも喜ばれる贈りものです。
母親向けの労いの贈り物をする場合も少なくありません。バスグッズやお茶など、リラックスできるギフトもおすすめです。このとき、既に持っているものと被らないように、可能であれば事前に希望をリサーチすると安心ですね。


「出産祝い」のNGマナー
出産祝いでやってしまいがちなNGマナーには十分注意しましょう。
たとえば、出産前に贈ることは避け、正式な出産報告を受けてから贈るのが安心です。 また、高額すぎる贈り物や、宗教・育児ポリシーに関わるもの(ミルク用品やお守りなど)も避けたほうが無難です。香りの強いものやアレルゲンとなる素材もNG。 さらに、勝手に自宅を訪問するのもマナー違反となります。産後は特にデリケートな時期。お祝いの贈り物は宅配で送るケースが一般的です。「おめでとう!受け取ってね」と事前に連絡を入れることも忘れずに。

よくある「出産祝いマナー」Q & A
Q.出産祝いを贈るタイミングを逃してしまいました。遅れても大丈夫?
A.生後2〜3か月以内であれば「遅れてごめんね」の一言を添えて贈れば問題ありません。出産してからも、お宮参りや100日祝いなど、贈り物をするタイミングはいくつもあるので、赤ちゃんの月齢にあわせてお祝いを贈ってもよいですね。
Q.二人目以降の出産でもお祝いは必要?
A.はい、お祝いの気持ちとして贈るのが丁寧です。ただし、初回よりも簡易な贈り物(絵本やおもちゃ、お菓子など)にとどめるケースも少なくありません。相手との関係によって贈り物を選らびましょう。
Q.出産祝いは、やっぱり直接渡したほうがいいの?
A.出産祝いを直接手渡しするのは丁寧で気持ちが伝わりやすい方法ですが、産後の母子は体力も気力も不安定な時期です。慣れない育児や睡眠不足などで心身ともに疲れていることも多いため、基本的には無理に訪問せず、宅配で送るのが相手への負担がなく好まれるでしょう。