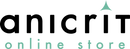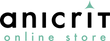「お歳暮」とは?
お歳暮とは、一年の感謝の気持ちを込めて、お世話になった人に贈り物をする日本の風習です。
始まりは江戸時代、年末に祖先の霊や神様に供え物を届ける「御供(おく)」の風習が、次第に目上の人や取引先への贈答文化へと発展したと言われています。
現代では、親戚・上司・恩師・取引先などへ、感謝と信頼を深める人間関係の節目のひとつとして、丁寧に対応したいですね。

「お歳暮」の5つの基本マナー
基本マナー1.お歳暮を贈る相手
お歳暮を贈る相手は、「お世話になった人すべて」ということではありません。日常的に深い関わりがあり、感謝を伝えたい相手に絞って贈り物をしましょう。たとえば、両親、義理の両親、上司、恩師、取引先などが一般的です。
基本マナー2.お歳暮を贈る時期
お歳暮は、贈るタイミングが非常に重要です。 本来の贈答期間は12月10日〜12月20日ごろまで。 地域によって若干の差があり、関東は12月初旬〜20日頃、関西はやや遅め(12月13日以降)が目安です。
間に合わなかったら年内に届けばよい、ということはなく、この期間を過ぎると「お年賀」や「寒中見舞い」として贈るのがマナーです。

基本マナー3.お歳暮の相場
一般的なお歳暮の相場は3,000円〜5,000円程度といわれます。 親族や友人、近しい人には3,000円前後、上司や取引先などビジネス関係には5,000円前後が目安です。
特別にお世話になった方には、もう少し高めの品を選ぶこともありますが、 高額すぎると相手に気を遣わせ恐縮してしまうため、注意が必要です。
基本マナー4.お歳暮の熨斗・表書き
熨斗(のし)とは、ご祝儀袋や贈りものに掛けるのし紙の右肩に添えてある飾りのことをいいます。 お歳暮の場合は「紅白蝶結び」水引を用いて、のし紙の上部中央の表書きには「お歳暮」と書き、 水引の下中央には贈り主の名前や会社名などを記載します。
実店舗やオンラインショップでは「お歳暮用」としておけば熨斗や表書きなどは自動で対応されます。
熨斗のマナーについてはこちらでも詳しく紹介しているのでぜひ参考にしてみてくださいね。

基本マナー5.お歳暮に適した贈り物
感謝の気持ちを伝えるお歳暮は、相手の好みに寄り添った品選びが重要です。 例えば、独身の方に大家族向けの食品セットを贈ると負担になることも。
人気のある品としては、ハムやお菓子、洗剤、コーヒーセット、調味料などがありますが、 アレルギーや宗教・健康面での配慮を忘れずに行いましょう。


「お歳暮」のNGマナー
お歳暮を贈る相手は「お世話になった人」というものの、公務員や一部の会社員などは、贈答品の受け取りが禁止されていることがあるので注意が必要です。 お相手の迷惑になる可能性もあるため、まずは「お歳暮をお贈りしても大丈夫ですか?」と一声かけると安心です。
また、感謝の気持ちを形にする風習のため、例えば複数人に贈る場合に「全員に同じギフトセットで済ませる」ということは”形式的”と受け取られかねません。 効率的ではありますが、相手に合う贈り物を選び、気持ちよく受け取っていただきたいですね。

よくある「お歳暮マナー」Q & A
Q.お歳暮は毎年贈らなければならない?
A.必ずしも毎年贈る義務はありません。ただし、継続して贈っていた相手に突然贈らなくなると「何かあったの?」と心配する方もいるでしょう。 贈らないと決めた場合は、「今年からはお気遣いに甘えさせていただきます」など、伝えておくのが丁寧です。
Q.お歳暮をいただいたらお返しは必要?
A.基本的にお歳暮は「お返し不要」の文化です。とはいえ、お礼の連絡(電話や手紙)は必須です。 もし頂きっぱなしがどうしても気になる場合には、 お礼を伝えたうえで、後日「お年賀」や「寒中見舞い」で簡単なお礼をしても良いでしょう。
Q.喪中のときはどうすればいい?
A.喪中でも、その一年の感謝を込めてお歳暮を贈っても差し支えありません。 ただし「お祝いごと」としての意味合いを避けるため、熨斗を外して無地の包装紙だけで贈るのが一般的です。 また、お相手が喪中の場合にも、同様に配慮が必要です。
Q.お中元をオンラインで手配してもいい?
A.最近ではオンラインでお歳暮を手配することも一般的です。 百貨店や専門店のオンラインサービスの中には、熨斗や挨拶文の同封にも対応するものもあります。 ただし、贈る事前に連絡を入れることと、実際に手に取ってみて選ぶことができないため、贈り物の情報を確認する心配りがポイントです。