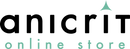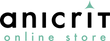「結婚祝い」とは?
結婚する二人に対して、幸せな門出を祝福し、今後の幸せや繁栄を願って贈る「結婚祝い」。
贈り物やご祝儀という形で表すのが一般的で、単なる形式ではなく、人生の節目を迎える相手への心からのエールが込められています。結婚祝いは、結婚式に出席するかどうかに関係なく贈ることができます。
式に招待された場合は「ご祝儀」を包むことが主流で、式に招かれていない場合や欠席する場合は、品物として贈るケースが多く見られます。

「結婚祝い」の5つの基本マナー
基本マナー1.結婚祝いをを贈る間柄とは?
結婚祝いは、基本的に「お祝いの気持ちを伝えたい相手」に贈るものですが、贈るべきかどうか迷うケースも少なくありません。まず確実に贈るべき相手は、家族・親戚・友人・職場の同僚や上司など、個人的に関係が深い人たちです。特に、結婚の報告を直接もらった場合や、式に招待されていない場合でも日常的に交流がある関係なら、お祝いの気持ちとして贈るのがマナーとされています。
基本マナー2.結婚祝いを贈る時期
結婚祝いを贈るタイミングは非常に重要です。一般的には、結婚式の1〜2ヶ月前から1週間前までに贈るのがマナーとされています。
式に出席する場合は、当日にご祝儀として現金を包むため、別途プレゼントを贈る場合はそれより前に渡すのが好ましいです。式の直前や直後は新郎新婦が多忙なことも多いため、相手の負担にならないように配慮することが大切です。
なお、結婚式後に結婚の報告を聞いた場合は、1ヶ月以内を目安に贈るとよいでしょう。

基本マナー3.結婚祝いの相場
結婚祝いの金額は、贈る相手との関係性や立場によって変わります。友人や同僚には1万円程度、兄弟姉妹などの近しい親族には3〜5万円、上司や目上の方からは3万円以上が一般的な相場です。
特に大切なのは、「割り切れる偶数」は避けるというマナー。偶数は「割れる=別れる」を連想させるため、奇数(1・3・5万円など)で包むのが基本です。ただし、最近では「2万円」はペア(2人)と捉える考え方も広がっており、1万円札1枚+5千円札2枚のように分けて包むと問題ないとされています。
また、あまりに高額すぎる贈り物は相手に気を使わせてしまうため、負担にならない範囲で設定することも大切です。連名で贈る場合は、人数で割って割り切れない額(例:3人で1万5千円)にするなどの工夫も必要です。金額に迷ったら、周囲と相談しながら調整すると安心ですね。
基本マナー4.結婚祝いの熨斗・表書き
結婚祝いにはのしと水引が必要です。水引の種類としては「一度きりで終わるべきこと」「繰り返さないこと」を意味する「「結び切り」の水引が最適とされています。間違って「蝶結び」(何度あっても良いこと)を選ぶと失礼にあたるため注意しましょう。
水引の色は「紅白」または「金銀」が一般的で、豪華にしたい場合は10本の水引が使われたものを選ぶとよいでしょう。
のしの「表書き」は、現金を贈る場合は「寿」または「御結婚御祝」が一般的です。品物の場合は「御祝」や「祝御結婚」でも問題ありません。名前の書き方にも気をつけて、フルネームで丁寧に書くのがマナーです。
熨斗のマナーについてはこちらでも詳しく紹介しているのでぜひ参考にしてみてくださいね。

基本マナー5.結婚祝いに適した贈り物
結婚祝いとして贈り物をする場合、相手の好みや生活スタイルに合ったものを選ぶことがポイントです。人気が高いアイテムとしては、ペア食器、グラス、キッチン家電、リネン製品など、新生活で役立つアイテムです。ただし、すでに用意している場合もあるため、相手の希望を聞いて贈るか、かぶっても差し支えのない消耗品を選ぶとよいでしょう。
カタログギフトも最近では非常に人気があり、相手が自分で好きな品を選べる利点があります。また、現金ではなく商品券やギフトカードを贈るのも、スマートな選択肢の一つです。ただし、包む際はのし袋を使い、祝儀としての格式を保つようにしましょう。


「結婚祝い」のNGマナー
結婚祝いを贈る際はNGマナーにも注意しましょう。
まず、贈るタイミングとして、結婚式直前や当日など、忙しい時期に送ったり持参することは避けましょう。ハサミや包丁など“切れる”ものや、時計や靴などといった「別れ」や「踏みつける」を連想させるもの、また、「偶数=割れる」「4=死」「9=苦」を連想させる数字はタブーと言われます。
「ペア」の意味合いがある2万円は例外的に許容されるケースがありますが、気になる場合は1万円+商品券などで調整するのも良い方法です。

よくある「結婚祝いマナー」Q & A
Q.結婚式に招待されなかった場合もお祝いを贈るべき?
A.はい。親しい関係で祝福の気持ちがあれば、招待されていなくてもお祝いを贈るのがマナーです。式の前後1ヶ月以内を目安に、贈り物やメッセージを添えてお祝いの気持ちを伝えましょう。
Q.結婚式に欠席する場合、お祝いはどうする?
A.出席できない場合もお祝いはの気持ちがあれば贈りましょう。結婚式の1週間前までに届くように準備し、欠席のお詫びと祝福のメッセージを添えるとより丁寧な印象になります。
Q.連名で贈る場合の注意点は?
A.複数人で贈る場合に気を付けたいのは、のしの記名です。右側から目上の人順で書くのが一般的です。また、記名しきれない場合は代表者名義でのしを書き、「○○一同」などと略す場合もあります。
Q.お祝いを現金以外で贈ってもいい?
A.お祝いとしては現金でなくても問題ありません。相手の好みに配慮した品を選びましょう。定番はカタログギフトや、二人の新生活に役立つアイテムなどです。迷う場合は事前に希望を聞き、必要なものを選んで贈るのもおすすめです。
Q.再婚の場合も結婚祝いを贈る?
A.贈る相手との関係性によりますが、再婚でも祝う気持ちがあれば喜んで受け取ってもらえるでしょう。
相手が負担に感じたり、気を遣いすぎない程度に、落ち着いた贈り物がよいでしょう。